あらすじ
救急医の武田の元に、ある日身元不明の心肺停止状態の男性が搬送されてくる。
海面に浮いているところを発見されたという。
彼は既に死亡していたのだが、その顔は武田に瓜二つだった。
武田は中学の同級生で医師である城崎と共に、その男性がなぜ死んだのか、自分とどんな関係があるのかを調べ始める。

本作は著者のデビュー作で、著者自身現役医師であるという。なるほど、院内の描写や心肺蘇生のシーンなどはリアルで、専門用語も多いのだが、読みやすい。
武田と共に事件を解決していく城崎は、整った美貌を持ち、感情に振り回されないタイプで、探偵顔負けの推理をしていく。彼のキャラクターが始めはありがちだなと思ったが、読み進める程に魅力が増した。
2人は武田の過去を調べていくうちに、過去に行われた不妊治療の事実を知ることとなるのだが、事件の真相には驚かされた。
心にグサっときたのは、「子を持ちたいという夫婦の願いを叶えることばかりに気をとられて、産まれてくる子供の権利と人権をあまりにないがしろにしてきたのではないか」という一文。確かに不妊治療と聞くと、どうしてもまずは子供が欲しくてもできない夫婦の思いにスポットが当たりがちだが、妊娠した先にある子を産み育て、共に幸せになることが目的なのだ。日本はドナーや子供を守るための法整備が進んでいないという。
親と血が繋がっていないと知った時のショックや、生物学的ルーツが分からないということがどれだけ人を不安にさせるのか、様々なことを考えさせられた。
次に読む本
『燕は戻ってこない』 桐野夏生
北海道で生まれ育ったリキは、これといった才能もなく、介護職で貯めたお金を持って上京し、病院事務の仕事に就くが、非正規雇用のため生活は苦しかった。
リキは貧困から抜け出すため、同僚のテルに卵子提供をすることを勧められる。しかし生殖医療クリニックへ行くと、そこで代理母出産を提案される。

代理母出産をすると決めたリキと、依頼した夫婦である基と悠子、それぞれの心情の変化がよく描かれている。
始めは2人の子供が欲しいという夫婦の思いが、いつしか基は自分の遺伝子を残すことに固執し、悠子は自分だけが蚊帳の外だと気付き夫婦の気持ちは離れていく。基の精子と他の女性の卵子で作った受精卵、さらに他の女性の子宮で産んでもらうのだから、悠子が疎外感を感じるのは当然だ。
そして、卵子ドナーにも、容姿や学歴といったランクがあるという話にはギクっとさせられる。さらに、妊娠・出産といった肉体的負担を負うのに、代理母出産を終えたら切り捨てられる。お金のために仕方ないとは言え、10ヶ月自分のお腹で育てた子を産んだ途端に手放すとはどんな思いだろうか。
登場人物全員が身勝手に思えるのだが、実際自分がそれぞれの立場に立たされることを想像すると、気持ちは分からなくもないかもしれない。ラストはなぜかすっきりした。
おススメポイント

どちらも不妊治療について描かれている。
この2冊を読んで特に感じたのは、やはり産まれてくる子供の人権を何よりも大事にしなければならないということ。
自分の子供が欲しい、遺伝子を残したいという思いは当然だが、血の繋がった親子でも子育ては大変なのだ。親の決断で産まれた子供は、血縁に関係なく、一生愛されるべきだ。
ただ、女性には妊娠して出産するという身体的負担に加え、精神的負担も伴うこともある。2冊とも女性の痛みがこれでもかというほど伝わり、胸が痛くなった。
文中に「倫理」という言葉が出てきた。何が倫理であるのか正解は分からないが、技術が発達して様々なことが可能になり、選択肢が増えた今だからこそしっかり考えたい。


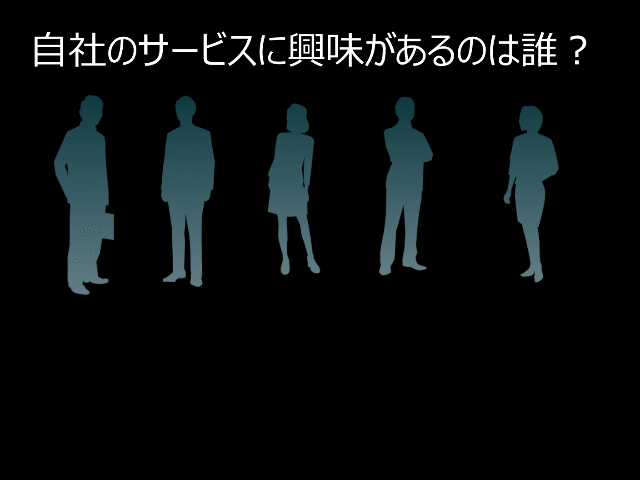 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す