あらすじ
「説明が上手な人」とは、相手の理解度に合わせて話を投げかけられる人のことだ。これだけだと単に「コミュニケーションが上手な人」というだけの話になるが、「難しい物事の説明が上手な人」は、それだけではない。
では、普通の人と何が違うのか。それは「具体と抽象を行き来できる」という点に尽きる。この力を持つ人の説明を聞くと、多くの人は思わず「頭がいい」と感じてしまうのだ。
この本が示している「具体と抽象を行き来できる人」とは、次の3つの特徴を備えている。
① 人によって具体と抽象の尺度が異なることを認識していること
「具体度が高まる」とは、「多くの人がわかりやすいと感じる」ということだ。しかし一方で、具体的であればあるほど「本質が見えにくくなる」という側面もある。そして、人によって「どの程度抽象的な話を理解できるか」という尺度は異なる。つまり、相手の理解できる範囲を見極めたうえで、できるだけ抽象度の高い話を投げかけることができれば、「この人は頭がいい」と思ってもらえるのである。
② 個々の具体に有機的な意味を持たせることができる
自分が聞き手の場合でも、何かアイデアを考える場面でも、具体と抽象を行き来する力は大いに役立つ。
たとえば、あなたが地元紙の記者だとしよう。
・地元のケーキ屋の記事(メディア未掲載)
・町の都市伝説の調査記事
・若者の行きつけスポットのインタビュー記事
これらは一見するとバラバラだが、「町の魅力を再発見する」という抽象的なコンセプトを掲げれば、共通の意味が見えてくる。
アイデアを生み出す人は、物事の共通点や違いを認識することが得意であり、そこから新たなアウトプットを生み出している。企業や仕事においても、理念や哲学といった抽象的な軸を持つことで、判断の無駄を減らし、物事に整合性を持たせることができる。
③ 想像力を掻き立て、自分なりの味を出せる
本書では、「パクリ」と「アイデア」の違いについても触れられている。
誰しも「これはさすがにパクリだな」と感じることはあるが、それを明確に言葉で説明するのは難しい。本書では、具体的なデザインや機能をそのまま真似ることを「パクリ」とし、抽象的な考え方やコンセプトを取り入れて新しい形にすることを「アイデア」としている。
例えば、有名な商品の形状や配色をそっくり真似るのはパクリだが、「誰でも簡単に使える」という抽象的なコンセプトを別の形で実現するのはアイデアだと言える。
新しいアイデアは、既存のものの組み合わせから生まれる。しかし、それには一定の抽象的な視点が必要だ。これを行き来できる人こそが、「具体と抽象を自在に操れる人」というわけである。
具体と抽象の行き来ができるようになると、相手に「わかりやすい」と思ってもらえるだけでなく、自分自身の思考の幅が大きく広がるのだ。本書は、その思考法の重要性と具体的な鍛え方を教えてくれる一冊である。

このうち、②の力――つまり「個々の具体に有機的な意味を持たせる力」の重要性を特に実感するのは、膨大な情報をただの暗記で終わらせず、バラバラの知識を一本の線として結びつけたいときだろう。日常の仕事や会話の中でさえ、物事の共通点を探し、意味を再構築する視点が自然と身についている自分に気づくはずだ。
だが、この感覚を「知識の世界」でさらに強烈に体験できるのが、実は受験科目の代表格ともいえる「世界史」である。教科書の知識を丸暗記するだけでは乗り越えられない東大の世界史の問いに挑むときこそ、②の力がいかにものを言うかがはっきりとわかる。本質をつかむ思考法と、膨大な具体をつなぐ力がどう交わるのか。その実例として紹介したいのが、意外かもしれないが次の一冊だ。
次に読む本
夢中になる東大世界史 15の良問に学ぶ世界の成り立ち(福村国春)
特に歴史が苦手な人にとって、歴史とは「暗記科目」というイメージが強い。しかし、東大の世界史は、ただ教科書に載っている人物名や年号を覚えるだけでは太刀打ちできない。
では、頭が良いとされる学生は、東大世界史をどのように解いているのか。
ここで必要になるのが、「個々の具体に有機的な意味を持たせる力」である。
歴史上の出来事が起こった国や年号、その時代の政治体制などの具体的な知識を正確に押さえつつ、その背後にある世界的な時代の流れや人々の思想の変化といった抽象的な背景を読み解く力こそが、東大世界史で問われている力だ。
本書は、歴史専門の大学受験塾で講師を務める著者が、東大世界史の実際の過去問を題材に、講師と生徒の対話形式でその解法プロセスを示した一冊である。ただ回答を提示するだけでなく、具体的な知識が抽象的な軸とどのように結びつくのか、その思考の流れを丁寧にたどることができる。

知識と知識が有機的につながり、そこから答えが導かれる過程を追体験できるため、内容としての面白さを感じられるだけでなく、読むこと自体が面白い一冊となっている。
おススメポイント

今回この2冊を選んだのは、「具体と抽象を行き来する力」という一見抽象的な思考法を、まったく異なる切り口から体験できるからだ。『具体と抽象』では、ビジネスや日常会話において物事をつなぎ直す思考の軸を学べる。一方で、『夢中になる東大世界史』では、ただの暗記で終わりがちな知識を有機的に結びつけ、背景の流れを読み解く力の大切さを実際の問いを通して追体験できる。
『具体と抽象』で思考の原則を知り、『夢中になる東大世界史』でその力がどのように実践で問われるのかを具体的に味わえる。この両方を読むことで、知識を知識で終わらせず、どこでどう繋ぎ、何を引き出すかという「考える面白さ」がより立体的に感じられるはずだ。


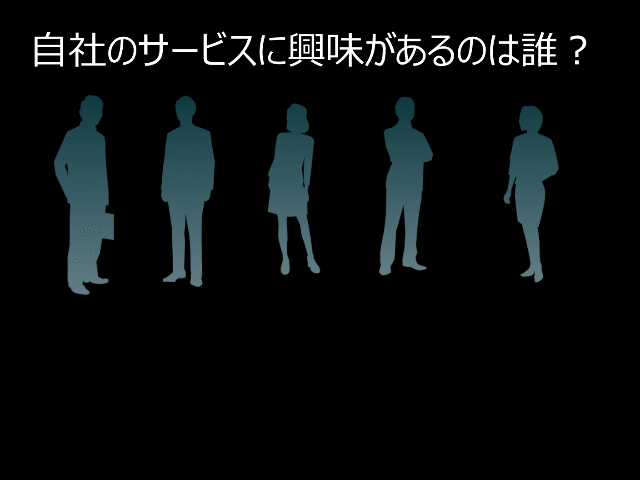 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す