あらすじ
バレエダンサーである萬春(よろずはる)は、8歳でバレエと出会った。15歳で海を渡り、ダンサーだけでなく振付家としての才能を開花させる。
1人の天才を、4人の視点から描いた物語。

著者の描く天才は魅力的だ。
この小説は、春と共にプロダンサーを目指す深津、春の叔父、作曲家の七瀬、そして春自身と、4人の視点から春について語られる。
他者が語る春の存在があまりに完璧で眩しすぎて、あり得ない設定だという意見もあるかもしれない。
しかし春自身の視点で描かれた4章では、天才にも苦悩があることに気付かされるし、春の人間らしい部分も垣間見えてほっとする。
システムそのものであった学校に居場所を見つけられなかった春は、バレエと出会い、胸が「カチッ」と鳴った。自分が「これだ」と思えるものに出会えたのだ。
人生において、これだと思えるものに出会い、その分野で類稀なる才能を発揮できる人がどれ程いるのだろうか。読みながら羨ましいという思いがフツフツ込み上げてくるが、それ以上に純粋に心地よくバレエの世界に浸れる小説である。
まるで少女漫画のような展開もあるが、登場人物たちの魅力と著者独特の会話術に引き込まれる。創作バレエの内容も読み応え十分だ。
私自身コンテンポラリーバレエを鑑賞するのが好きなのだが、文中の「舞台の上のダンサーは観客の代わりに『生きてくれている』。誰もが舞台の上で『生き直す』自分を観ている。舞台の上のアーティストと一緒に、人生を生き直す。」というセリフは特に印象に残ったし、何かが腑に落ちた気がした。
次に読む本
『掌に眠る舞台』 小川洋子
バレエ『ラ・シルフィード』を観て感動し、ラ・シルフィードに手紙を書き続ける少女の物語、『レ・ミゼラブル』の全公演に通う女性が出会った劇場で暮らす「失敗係」の物語など。
「演じること、観ること、観られること」、舞台にまつわる不思議な世界観を描いた短編集。

どの物語も著者独特の不思議でひっそりとした静かな世界観に引き込まれる。
特に印象に残ったのが「指紋のついた羽」である。父親が金属加工工場で働いている少女は、バレエ『ラ・シルフィード』を観てからずっとラ・シルフィードに手紙を書き続ける。ラストで彼女が工具箱の上でペンチやスパナを使い『ラ・シルフィード』を上演するというシーンがあるのだが、だいぶ奇妙なシーンにも関わらず、著者が描くと御伽話のような幻想的な場面にも思えてくるから不思議だ。
煌びやかなスポットライトを浴びた華やかな舞台を描くのではなく、それを観る人や観られるということに焦点を当てており、どこか不気味さを感じる話もあったり、様々な側面を持つ短編集である。
おススメポイント

どちらも舞台にまつわる小説ではあるのだが、内容は対照的である。
これでもかという程眩しい華やかな舞台を描いた『spring』に対し、『掌に眠る舞台』は、舞台を観て憧れる人や、演じる人であっても決して目立つ役回りではない人に焦点を当てており、読後に少し寂しさすら感じるような内容だ。
2冊とも舞台を通して様々な感情を掻き立てられる小説で、お勧めしたい。


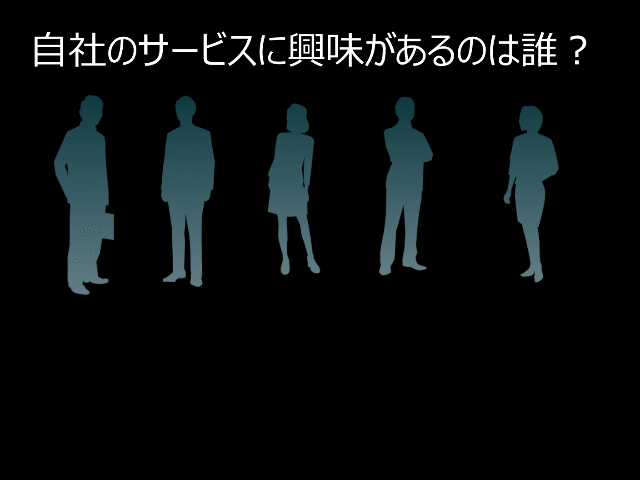 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す