あらすじ
日本の首都でもあり、多くの人が暮らすまち、東京。本書では、縄文時代から、東京がどのように発展してきたかを概観する。
戦国時代の末期に徳川家康が領主になり、のちに家康が江戸幕府を開いたこと、明治時代に天皇陛下が東京へお遷りになったこと、などがあって、現在の東京がある。
20世紀に入り、荒川の放水路を新たに作り、現在の墨田川への流入を岩淵水門で制御することで、水害を大きく減らした。

NHKの番組『ブラタモリ』が好きな人に刺さりそうな本です。
トピックは多岐にわたりますが、その分、掘り下げは浅めです。巻末の参考文献などを参考に、興味をもったトピックに関連する本を読むと良さそうです。
次に読む本
人がつくった川荒川(長谷川敦)
埼玉県の西端(山梨・長野との県境)から埼玉県を横断し、東京都の東部を通り、東京湾へそそぐ荒川。河川の氾濫で苦しむこともあったが、利水として、また舟運として活用されてきた。
荒川放水路は、1,300軒の立ち退きで実現した大事業。このおかげで、水害が大きく減った。
水害を防ぐ・減らすのは行政だけでなく、各々の家庭でできることがある。雨水浸透ます(住宅に降った雨水を、地面に浸透させる)を設置したり、大雨時に生活排水を控える、など。
荒川のごみ拾い活動も紹介されている。

雨水や生活排水を各家庭が控えることで、大雨時の水害が少しでも減るのなら、一人一人ができることを実行していきたいですね。
荒川のごみ、元をたどれば捨てている人間がいるのですよね。川を汚さない努力、こちらも一人一人の行動が積もり積もって大きな差になりそうです。
おススメポイント

『東京ができるまで』で取り上げられていた荒川放水路から、『人がつくった川荒川』に繋ぎました。
川の流れを変える大事業には驚かされました。その結果、水害が減っています。現在の東京は、過去の人々の活動のおかげで維持・反映しているのだなあと実感しました。感謝しなければいけませんね。
『人がつくった川荒川』では、未来に向けて、現在の我々ができることも触れられていました。過去の人々に感謝するだけでなく、実際に行動することが大事に思いました。


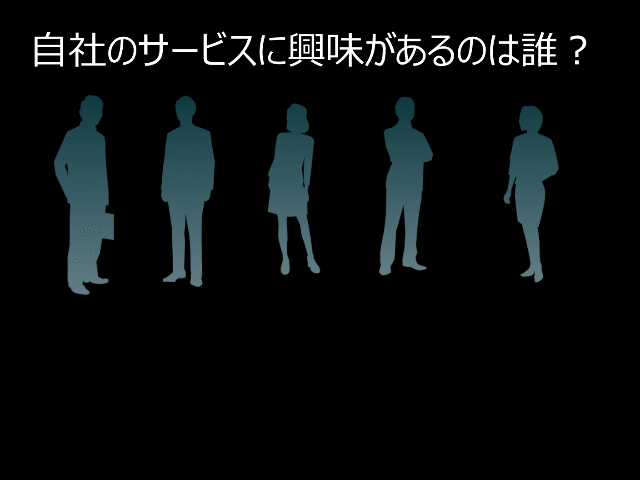 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す