あらすじ
現在、日々いろんな情報が洪水のごとく流れている中、コスパ、タイパを重視する人が増えている。
仕方がないのです。
スマホを開くと次々と興味のある情報が表示される。
欲張りなので全部気になる。
一つのことに長くとどまる時間がなく、ついつい浅く広く情報を得る。
果たして、身についているのか。
そんな時でも、少しスマホを置いて、読書する時間を確保する。
しかも時間がないから速読〜という形ではなく、あえて『遅読』をする。
本書は読書することにあたって、遅読がなぜ必要なのかを教えてくれます。

「読書は自分の人生を豊かにするもの」だからこそたくさんの本を読むのも一つの考え方だけど、1冊の本の内容をどれだけ自分の中に取り入れることができたか!
それも同時に重要だとこの本を通して強く伝わりました。
読みたい本がある私はついつい駆け足で読もうとしてしまいます。
それでも、ん?何か気になる、気づくと読む速度が落ちてしまっている時があります。
でもそんな読み方でもいいんだ!
読む本によって、単に今の情報を取り入れたいときは遅読より速読でもいい。
読み方を変えるのもありだと。
読書は知性の足腰を鍛えることができる。知性の足腰が弱いと価値や物事の判断ができず、間違った情報に流されてしまう。
著者の意見に大変納得ができました。私は元々好奇心旺盛でしたが、本を読むようになってますます色んなことに興味がわき、色んなジャンルの本を読むようになりました。
例えば、古事記や哲学の本。難しいだろうなと思うとなかなか手がつけれませんが、活字ばかりでなく、漫画だったり、関西弁で書いていたりすると、クスッと笑えて読むことができる。
次はもっと深入りして知りたくなり、活字たっぷりの本を手にしてしまいます。
そして、なんでこうなる?もう少し掘り下げて物事を考えるくせができました。
また、著書はこの本の中で遅読に向く本をたくさん紹介されています。私もその中に気になる本が多数見つかりましたので、早速購入しました。
次に読む本
遅読家のための読書術/印南敦史
この本は、本を読むのに時間がかかる人に対して、考え方を変えてもっと読書に向かえる方法を教えてくれる本になっています。
この本も、現在の情報洪水の中をスマホをよこに置いて、本を手にしたくなる気持ちにさせてくれます。

私がこの本で一番心に引っかかったのは、いくら熟読していても人は忘れる。その中でも忘れていない部分が一つはある。
そのひとつのかけらを集めて大きな塊を作ることができると。
そうすることにより読書の幅も広がる。
一字一句きっちり読まないといけないと思えば思うほど、本は読めなくなる。
今は日々洪水のごとく情報が流れる。
そんな時代にあった読み方をするのがベストだと。
私も一冊読み切ったと!思いたいからついつい読み飛ばさず読む。
ただそれは自己満足なんですね。
面白い本、自分に合う本、色んな素晴らしい本がたくさんあるので、生きているうちに1冊でもたくさんの本に出会いたいと思うのなら、自己満足、固定概念を捨てて
本に向き合うべきですね。
おススメポイント

『遅読』というキーワードを切り口に、たくさんの本に向き合ってきた二人の著者の考えを読み比べるのはおもしろいかなと思い選んでみました。
二人の共通点は本のジャンルによって速度するのはいいとされています。
それと、とても大事なこと。
本を読む人生と読まない人生を比べると、本を読む人生のほうがはるかに楽しく、豊かな人生を送れると話されています。
反対に、遅読については、1冊の本をあえてじっくり時間をかけて深読みすることで知性を鍛えることができると、
「遅読」のすすめでは、遅読を推しています。
遅読家のための読書術では、自分自身は遅読家だから、読むのに時間がかかる。
まして今の情報過多の時代に本なんて読んでる時間はない。
と考えるのではなく、今の時代にあった読みかたをする〜流れるように読む〜
周りでは「遅読」より速読の方がイメージがいいように思えます。
この2冊の本を通して読み方の固定概念を捨てて、素直に読書に取り組む姿勢が作れるようになる気がしました。


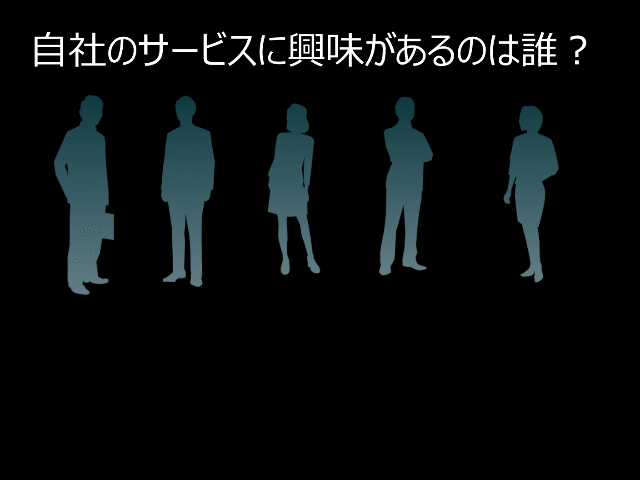 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す