あらすじ
AIが文章を書く時代、ネットでは検索ボリュームが文章の評価を決める。
そのため人はAIの検索エンジンが高いキーワードを組み合わせた文書をAIに委ね短時間に大量の文章を作り投稿する。そこに書き手の思いや体験が綴られた文章なのかは必要なくなってきてしまっているのが昨今の事情です。
でもそれが唯一今のAIには書けない欠点でもあります。だからこそ自ら文章を書くことについての意義を本書では紐解いています。
まずは私達が何気なく使っている言葉がいかに曖昧な表現かということを知る。
これによって何が起こるかというと読み手によって受け取る意味や解釈が違ってきます。そこで次に必要なのが言葉を情報に換える文を作る。
筆者は下記の点を指摘した文章作法を考案し、AIに書けない文章を書く事に繋がる書き方を解説しています。
・よく文の書き方を習う時5w1H で書きましょうと習うが実は多くの人が書く文は4w1dで作られている事がほとんどです。忘れがちなあと1つのW=WHYを書いた文章に組合わせる。
・文章は、骨を書き肉付けする。接続詞や修飾しがちなのをなるべく削ぎ落としよりシンプルに、端的に書く。
・AIが書いているのは文章ではなく文書である。文章と文書の違いを明確にする。
様々な文章例を使って文章が出来る過程を説明してくれます。
作者が思う文章作法で書くことが私たち人間がなぜ文章を書くのかという意義と役目を考察しています。

最近、仕事や会議においてAI生成によって文章構成や資料を作ることが導入されてきています。でもまだまだ機械的な書き方だなと作成された文章を見て思った事があります。
それが本書を読んでAIと人の書く文章の違いがどこにあるのかについて読み解き解説されていてなるほどとなりました。
逆を言うとこの本で筆者が考察している文章の書き方を意識出来ないともうそれはAIにも書けてしまう文章だという事。自分の代わりは既にできてしまっているのです。このように書評を書いたりブログを綴ったりしている身としてはそこに危機を感じました。
記者として書くことの熟練した知識を持った筆者だからこそやや文法的な説明が多いですが、是非文書ではなく文章という定義が理解すると自身の書き方が変わるしこのAI時代に負けない書き手になることが出来ると思います。
次に読む本
頭のいい人の、学びを「20字」にまとめる技術(浅田すぐる)
本書では、20文字で端的にまとめ伝える方法を教えてくれます。
・たった20字で伝えたい事をまとめる。
・3つのポイントでわかりやすく伝える。
・紙一枚書くだけのインプットで作っていく方法を教えてくれます。
そして次に分かりやすく説明する為のアウトプット方を学びます。
人は説明を聞くとき、3つの疑問(何、なぜ、どうして)が解消されたときわかりやすいと判断するといわれています。
この3つの疑問を解消するように説明すれば大勢のよくある説明から抜き出たわかりやすい伝わり方へと変身をとげるのです。最後にこの学びを活かすと仕事において何が出来るようになるか。
それは他社に貢献できるようになるのです。人にわかりやすく説明して、疑問を解消できた時きっと周りの人の役に立つことが出来た瞬間に立ちあえる。
その他社貢献こそ仕事になり、人に求められる需要を生み出す、しいてはビジネスになる。
作者自身、独立後この意識が芽生えた時から自分にしかできないビジネスが生まれ今に至るまで飛躍を遂げてこられた経験から仕事の流儀についても教えてくれます。

ただ文章をわかりやすくまとめたい、読書や学んだ事をアウトプット上手になりたいと手にとりました。すると読み進めていくうちにまとめ方だけではなく何事も学んだ事を活かして人に役立てる事が需要になり、仕事になる。働くとは自己の実現の為ではなく他社貢献であると言うビジネスに繋がっていく道理を解き明してくれ読み終えた時にこんなに深い本があるのかと感嘆したのを覚えています。
私も読む人がわかりやすいと思ってもらえる事、疑問が解消される事など対相手の目線に立って書く、伝える大切さに気付かされました。
実践的に 紙一枚という手軽さで取り組みやすく、格段に自身の伝え方がブラッシュアップされるのを感じられました。
おススメポイント

文章を人間が書く意義を見つけたら次はそれを人に直接伝えることも人にしかできない役目だと思います。
ならば人にわかりやすく伝えるまとめ方を学びたい。または会議やプレゼン、発信をする時に上手く伝わっているだろうかと不安になるときはありませんか。
そんな方に是非おすすめの端的に分かりやすくまとめる極意が書かれた本です。


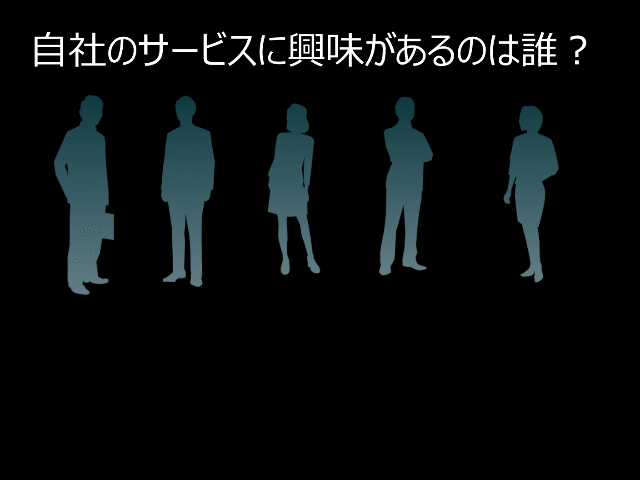 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す