あらすじ
「感謝すること」「感謝を伝えること」の大切さは、誰もが知っているでしょう。
本書は、あらためて「感謝の本質」を見つめ直し、日々の中で感謝を感じる習慣を身につける方法を紹介する一冊です。
感謝に関する本には、大きく二つのアプローチがあります。
一つは、心理学や脳科学をもとに感謝の効果を分析する科学的アプローチ。
もう一つは、感謝を人としての徳や道として説く倫理的・道徳的アプローチです。
本書はその両方の視点を踏まえたうえで、「感謝を感じるための思考法」や「感謝を軸にした人生の姿勢」について問いかけます。
著者は「感謝=幸せ」という考えを軸に、感謝と幸福の関係を明確にし、より良い感謝の習慣を築くための考え方や視点を紹介。
また、偉人や著名人の名言を引用しながら、日常生活の中で感謝の心を育てるヒントを示します。
当たり前になりがちな「感謝」や「幸せ」、そして「人とのつながり」を改めて見つめ直すことで、現代を生きる私たちに多くの気づきを与えてくれる一冊です。

本書を読んで、これまで自分が使ってきた「感謝」の言葉が、どこか形式的なものになっていたことに気づかされました。
日常生活の中で「ありがとう」と口にする機会は多いものの、その言葉に心が伴っていなかった場面も少なくなかったように思います。
感謝の言葉を言う回数と、実際に感謝の気持ちを感じる回数は、必ずしも一致しない。このことを改めて実感しました。
特に印象に残ったのは、「他責=自責」という考え方です。他人を責めることは、結局は自分を責めているのと同じである、という本書の指摘に深く共感しました。
この考え方は、感謝や承認のあり方にもつながるものだと思います。
他人に対して心から感謝や賞賛を伝えられない人は、他人からの承認を素直に受け取ることも難しいのではないでしょうか。
その結果、努力しても報われない、満たされないという感覚に陥ってしまうのだと感じました。
この気づきを通して、普段は当たり前だと思っていた他人の存在や環境、身の回りの出来事のありがたさを、もう一度丁寧に見つめ直す必要があると感じました。
また、現代社会ではお金や地位などの外的な尺度が幸福の象徴とされがちです。
しかし本書や各種の研究が示すように、金銭的な豊かさによって得られる幸福には限界があります。
私自身も、これまで世間の常識や他人の評価に左右されて生きてきたことを反省させられました。
幸福の基準を少し下げてみることで、これまで「当たり前」と思っていた日常の中にも感謝や喜びを見いだせるのではないか――そう感じたことも、この本の大きな魅力の一つでした。
さらに、最後に紹介されていた「承認の振り返り」というワークも印象的でした。
自分が認められたことや評価されたことを記録することで、他人からの承認を見逃さず、自分の存在価値を再確認できるという内容です。
私たちは、知らないうちに他人に求めるハードルを高く設定し、相手の善意や気遣いを当然のものとして受け取ってしまうことがあります。
そのような無自覚な態度が、結果としてお互いを苦しめているのかもしれません。
本書を通して、自分にとっての「幸福」とは何か、そしてこれからどのように生きていくべきかを改めて考える貴重な機会となりました。
これからは、感謝や承認といった目に見えない価値を大切にしながら、一日一日を丁寧に生きていきたいと思います。
次に読む本
『言葉にする習慣 思いがまとまる・伝わる 「言語化力」の身につけ方』 さわらぎ寛子
「言いたいことがあるのに言葉が出てこない」
「感想にヤバい、すごい、しか出てこない」
「何を言ったらいいか分からない」
そんなふうに、うまく言葉にできない・伝わらないというもどかしさを感じる人は多いのではないでしょうか。
本書は、3万件以上のキャッチコピーを考えてきた現役コピーライターが、思考を言葉にし、伝わる形に整える方法をまとめた一冊です。
内容は大きく二部構成になっています。
① 自分の意見や思いを整理・分析する方法
② 相手に伝わるように表現する方法
著者はまず、「どう伝えるか」というテクニックよりも前に、「何を伝えたいのか」を言葉にすることが大切だと説きます。
そして「自分らしい言葉」とは、「その人なりのものの見方」と「その人らしい言葉選び」から生まれるものだと述べています(pp.9–10)。
本書では、自分が何を言いたいのか、どんな意見や目的を持っているのかを観察・分析する思考法を紹介。
さらに、そこから引き出した言葉を相手に伝わる形にするためのメソッドも丁寧に解説されています。
言葉にする習慣を身につけたい人にとって、本書は実践的なガイドになります。
仕事・学業・趣味・SNSやブログなど、あらゆる場面で「伝える力」を伸ばしたい人におすすめの一冊です。

これまで映画を観たり本を読んだりしても、感想を聞かれると「よかった」「面白かった」といった一言で終わらせてしまうことが多く、うまく言葉にできないことが悩みでした。
そんなもやもやに対して明確な答えを示してくれたのが、本書です。
著者は、「感想が書けないのは、一つ一つの理由をすべて“面白かった”という大きな袋にまとめてしまっているからだ」と指摘します。
「面白かった」という感想の中に含まれている状況・感情・思ったこと・理由などを丁寧に掘り下げていくことで、感想の解像度を高められると説いています。
自分がなぜそう感じたのかを言葉にすることは、単なる感想を超えて、自分の考え方や価値観を見つめ直す行為でもあると気づかされました。
言葉にできないのではなく、考えを整理する習慣がなかったのだと痛感しました。
さらに印象的だったのは、「伝える目的を明確にする」という考え方です。
相手に共感してもらいたいのか、それとも行動してもらいたいのか――その目的によって言葉の選び方や伝え方は変わります。
これまで何となく話していた自分に気づき、今後は「相手にどうなってほしいのか」という未来まで意識して伝える姿勢を大切にしたいと思いました。
また本書では、思考を整理し言葉にするための実践的なメモ活用法も紹介されています。
日常の中で「自分ならどう伝えるか」「どう感じたのか」を書き出す習慣を通して、表現力やメタ認知を磨いていきたいです。
本書は、自分の感じたことを自覚し、他者に伝える力を養うための指針となる一冊でした。
おススメポイント

今回、1冊目として選んだのは『感謝のチカラ 「今ここ」に生きる: 快適中毒から抜け出すための上手な感謝のしかた』です。
この本を通して、感謝を感じる習慣や幸福について改めて考えるきっかけを得ることができました。特に第7章では、「何が幸せか」「どう生きたいのか」「どんな価値観を大切にしたいのか」を言葉にして見つめ直すことの重要性が語られています。
そこで2冊目として、『言葉にする習慣 思いがまとまる・伝わる 「言語化力」の身につけ方』を選びました。
この本では、自分の考えを観察し、分析し、言葉にする力を磨く方法が紹介されています。感謝の気持ちを相手に伝えるためにも、「何がありがたいのか」「どんな状況でそう感じたのか」を的確にフィードバックする力が欠かせません。言語化のスキルは、そのための大きな助けとなります。
この2冊を続けて読むことで、自分の生活を見つめ直すと同時に、人との関わり方や感謝の伝え方を深めることができます。
ぜひ、手に取って読んでみてください。


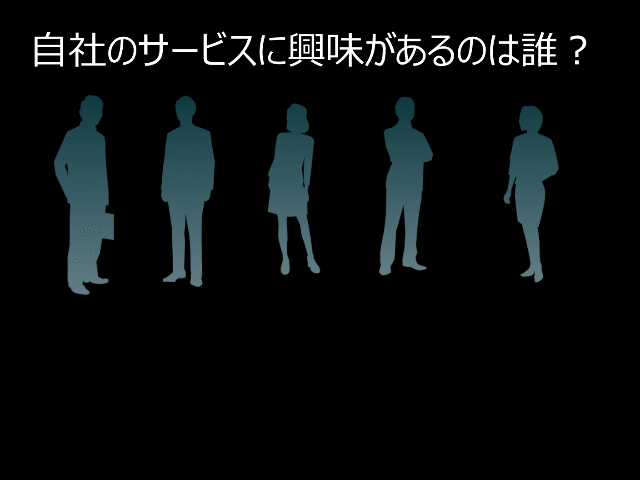 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す