あらすじ
本書は、「話が面白い人は何をどのように読んでいるのか」という視点から、読書や情報との向き合い方を解説した一冊。著者の三宅さんは、作品を単に楽しむだけでなく、「ネタを仕込むつもりで読む」ことの重要性を説きます。
本書で紹介されるポイントは主に次の3つ。
1. 逆算して読む:
・読む前から「自分に何を生かせるか」を意識する。
2. 抽出と整理:
・作品から得た情報や感覚を、自分の引き出しとして整理する。
3. 会話に活かす:
・読んだ内容を、日常の会話や雑談に応用できる形に変換する。
単なる知識の習得ではなく、自分の体験として消化し、会話や思考力に生かせる力を育てることができます。

私の周りにも、話が面白い人って多いですが、
よく観察してみると、彼らはただの自信家ではなく、話の引き出しが多いように思えます。
三宅さんの本でも、冒頭に「ネタを仕込むつもりで本を読みなさい」とありますが、まさにこの感覚。
読む前から「自分に何を生かせるか」を逆算して読むことで、作品の面白さを会話に変換できるんだなと、改めて実感できたのはこの本のおかげです。
さらに、この逆算の視点を持つと、ただ面白いと感じるだけでは見逃してしまう小さな発見や気づきも拾えるようになります。
つまり、作品を楽しむだけでなく、自分が変わるきっかけを作ることもできるということです。
例えば、映画のちょっとしたセリフや描写から、日常で使える比喩や話のフックを見つけられたり、
読書や映画鑑賞が、単なる娯楽から会話力や思考力を育てるトレーニングに変わる、そんな実感を教えてくれる一冊でした。
次に読む本
チーズはどこへ消えた?(スペンサー・ジョンソン)
物語の主人公は、2匹のネズミ(スニッフ、スカリー)と2人の小人(ヘムとホー)。
彼らは迷路の中で「チーズ」を探し回ります。
このチーズは、仕事の安定やお金、地位、愛情など、人それぞれが大切に思うものの象徴です。
ところが、ある日たっぷりあったチーズが突然なくなってしまう。
ネズミたちはすぐに新しいチーズを探しに迷路へ向かいますが、小人たちは現状に固執して動けません。
物語は、変化にどう対応するか、恐れや不安にどう向き合うかを寓話を通して描き、読者に「変化を受け入れ、一歩踏み出す勇気」を教えてくれます。

変化が訪れると、不安や迷いで立ち止まってしまうことってありますよね。
私も「このままでいいのかな」と立ち止まることがありますし、今もライフプランの途中で迷う瞬間がよくあります。
『チーズはどこへ消えた?』は、迷路でチーズを探すネズミと小人の物語を通して、変化にどう向き合うかを教えてくれる一冊でした。
誰だって変化は怖いものですし、目の前のチーズ(幸せ)にしがみつきたくなる気持ちはあると思います。
ですが、本当に大切なのは、まず勇気を出して一歩踏み出すこと。
もちろん、変化には怖さや失敗が伴いますが、それを乗り越えた先に本当の幸せがある――この本を読んで、改めてそう感じました。
おススメポイント

『チーズはどこへ消えた?』をおすすめする理由は、今の幸せが当然なくなってしまうかもしれない、ということを教えてくれる点です。そして、その幸せが失われたとき、どう行動するかが未来を大きく左右します。一見当たり前のことのようですが、自身がその状況に置かれたらどうするかを考えさせてくれます。
言い換えれば、自分が行動に移す前の心構えや考え方を整えることの大切さを教えてくれる本でもあります。目の前の安心にしがみつきたくなる気持ちも理解しつつ、新しいチーズを探す一歩を踏み出す勇気を、寓話を通して自然に学べる一冊です。


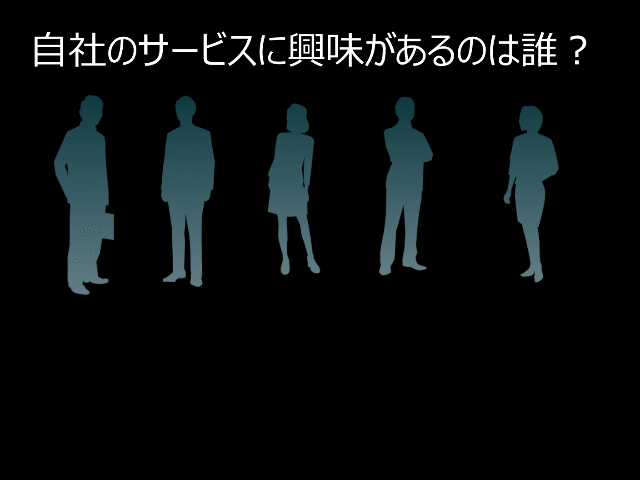 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す