あらすじ
著者の二十四歳から四十七歳までの随筆をまとめた一冊。一編一編は短めで読みやすく、親しい友人の日記兼語りを見聞きしているような印象もある。
知的で、豊かな感情と論理的な理性の両面が垣間見えるのも魅力である。
著者が自分の生きる意味を、手応えを持って知るための、人生の軌跡を読ませてくれる。

「ささやかな日常の輝きを照らす やさしく温かな心の光」というサブタイトルから、ものやわらかな文章を想像したが、どちらかと言うと、とても知的で端正な文章であった。20代は、自分のために自分を磨く。30代は、新たな家庭の主である夫と、その家族のために、自分を成熟させ、絆を作ってゆく。40代は、そこまでに習い覚えた物事を、他の人のために存分に分かち合う。
そんな大まかな人生の流れが見える。
私は、優しさの記録というよりも、著者の天野さんが、自分の存在価値を再構築してゆく歩みの記録にも見えた。
手話・手芸・洋裁・英会話・ヨガ・日本語ボランティア等々、多くの習い事を通じて、その中で培った知識を、ただのお楽しみでは終わらせない。誰かに分かち与えてゆくこと、人を支える技能にしてゆくことで、天野さんは「何事かを成す人」と自分を認めてゆく。
人を支えることで、自分が確かな存在意義を持つ、その記録として読めるのだ。これは彼女がカウンセラーであることも、影響しているだろうか。
私個人は、お稽古事、習い事をしていない。あると言えば、社会人になってから、歌が好きだったので、プロの先生について歌のレッスンをしてもらっていたくらい。親は、お稽古事などあまり意味がないと考えるタイプで、洋裁和裁・華道や茶道・料理も、母自身、ちょっと出来るようになると、辞めて独習に切り替えてしまい、実用一本槍だったらしい。
私はそういう中で育って、お稽古事なんて、してどうするのだろうと思っていた。しかし、この本を読んで初めて、考えを変えた。
人生の余白を作り、そこでいろんなことをやってみるのも、確実に日々を豊かにするのだ。もしも天野さんが、仕事だけしている人だったら、この本に語られた、他者への関わりは生まれず、ご自身も、真面目だけれど、ちょっとだけ無味乾燥な思いを、どこかに秘めてお暮らしだったかも知れない。
私なら……私は今、無駄とか結果はどうでもいいから、やりたいことがいくつあるだろう。正直に告白すると、一時期「なにもない」と答えていた事がある。
東日本大震災やコロナ禍を経て、どこか不安な日々が続く今。
お金が大変なら、母を真似て独習でもいいから、やってみたかった憧れを、やってみようか。少なくとも私がイキイキするだろうといのは、確かだし。
そういう、新たなチャレンジが、新しい繋がりや知識を連れてきてくれるかな。
今年の冬こそ、マフラー以外のものを編み上げよう。
無理だど言ってないで、音声配信もやってみよう。
イタリア語もやっぱり、単語で良いから覚えてみたい。
着物のコーデも、着なくてもいいから詳しくなりたい。
歌だってやりなおしたい。
ほら、やりたいことあった。私は、これから何を知って、そこでどんな人の軌跡に出会うだろう。引き出しは、下手っぴでも、多ければ多いほど良い。
何がどこで役立つかなんて、わからないではないか。
少なくとも、退職して趣味を探している母とおしゃべりしてあげる、タネは増えそうではないか。誰かに、私もなにか、手渡せそうな嬉しさが、小さく芽吹いた。
次に読む本
「ひとりだと感じたときあなたは探していた言葉に出会う」若松英輔 (著)
孤独に迷った時、傷ついて立ち上がれない時。その時こそ人は、自分が何を求めていて、どんな生き方がしたいのか、一番はっきり知る時である。内省と自己探求の時間に、誰かとの予期せぬふれあいが重なると、自分自身でその傷を癒やして、また歩き始める事ができる。
読書・信仰・人への分かち合い、支え合いの中から、著者自身も癒され、周囲の多くの人も、ともに育まれていく。
自分をみつめ、迷う時間を豊穣に感じさせてくれるエッセイ。

若松英輔先生のこ゚本は、読後すぐには、なかなか感想が書けない。とても満たされた感覚と、自分のつらい事どもが、ふと包帯が取れたように楽になっているのに、その理由が、言葉ではなかなか言い表せないからである。
しかし、傷ついた理由、苦しんだ理由なら自覚できても、どうやって立ち直ったかは、意外と言葉にならないものではないだろうか。
「この出来事を引き受けられるのは、自分しかいない」
という自覚と、
「いつまでも立ち止まりすぎるのは、却って事態を難しくし、自分の立ち上がる足を重くしてしまう」
という気づきを持った時、そこに思い至った理由は自覚できなくとも、よいしょと痛む身体と心を伸ばし、ようよう歩き出すものではなかろうか。
本書を始めとする、若松先生のご著書は、そういう心の経過を、停滞と捉えずに、豊かな時間として肯定してくれる優しさがある。
自分にとっては、もしかしたら人生過去イチの情けない期間であったかもしれないのだが。振り返ってみれば、そこからまた歩き出したという経験が、人生にほのかな自信を与えてくれることでもある。
更に言えば、その経験を共有し、誰かが座り込んでいるところに、そっと自分ができる何か、小さなこと。笑顔を見せるだけでも、肩に触れてぬくもりを分けることでもいい。出来たなら、また立ち上がる人がいるかもしれないのだ。
苦しみは個人的なものだが、その先で見つけた小さな行く手の光は、誰かと分け合うものである。あるところまで併走しても、人はいつかまた独りで行程を歩む。
その繰り返しは、案外悪くないよと、本書は静かに教えてくれる。
本書は、ごく普通のエッセイなのだが、カウンセリングやセラピーの、基本的な考え方――自分に潜む、自己再生の力と、踏み出す勇気を自覚できるまでの伴走者が、カウンセラーを始めとするセラピストの存在意義であり、クライエントにセラピスト側も、併走してもらっているのかもしれない。人生の一時期の出会いと共存、その後の穏やかな別れが、セラピーの本質かもしれない……などという気付きも与えられた一冊である。
おススメポイント

最近、エッセイがまたブームであると言います。(「随風」というエッセイ専門誌が創刊され、話題にもなりましたね。)日常のあれこれを細やかに綴ったエッセイは、身近で小説にはない親近感や楽しさがあると思います。
当初、そういう味わいを期待して『随筆集 波紋を掬う : ささやかな日常の輝きを照らす やさしく温かな心の光 』を読み始めたのですが、ちょっと思っていたのとは違いました。
人は、いつでも
「誰かのために何か、意味のあることをしたい」
のだということ。そのためには、意外と、
「なんとなく始めた、自分のための好きなこと」
も、役に立ったり、人を支える力になってくれるのだ、ということを、この本から強く感じました。
この本が個性的なのは、単なる自分探しや自己満足で終わらずに、誰かにまじめに関わって、得たものを分かち合ってゆきたいという、著者の姿勢によると思います。
自分の空白を埋め、自分を癒やしたあと、そこで終わらずに、出会った人と自分の経験も痛みも含めて、誰かと共有しよう、次は相手を励まし支えよう。それこそが豊かな人生の幸福の連鎖だ、という姿勢は、
2冊めに選んだ若松英輔さんの『ひとりだと感じたときあなたは探していた言葉に出会う』にも、共通しています。
面白おかしい、気が楽になるエッセイではありませんが、どちらも読み終わると、冷たく清涼な水をたっぷり飲んだように、また明日も頑張ろうかな?と感じさせてくれる本たちでした。
無駄なことなんて、本当は何もなくて、咲かせ方次第で、幸せの花の種は、もう手の中にある、そういう読後感が支持される理由ではないでしょうか。


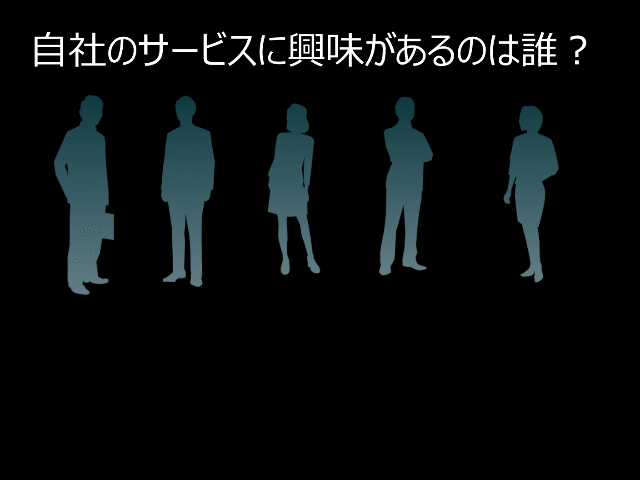 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す