あらすじ
AIの進歩やSNSの普及により、現代人は文章を書くという行為から遠ざかっている。
文章とは、「書き手の思考や感情がほぼ表現し尽くされたもの」である。生成AIが書くものはネット上にある情報やデータをまとめた「文書」であり、私たちの思いを表現することはできない。
言葉をつないで、自分にしか書けない思いを文章にするには何が大切なのか…元朝日新聞校閲記者が、文構造のルールや相手に伝わりやすい文章の書き方を説く。

故谷川俊太郎は昨今の言葉について、「量が増えたが、質が薄っぺらになっている」と話していた。どの時代にも流行語はあるが、最近のSNSなどで飛び交う略語は元の言葉よりもかけ離れたものが多く理解に苦しむ。もはや日本語ではなく、品がないと感じる。また、学校で作文を書く機会もだいぶ減っているし、年賀状もメールで送る時代になった。
確かに、AIにおまかせすれば、ある程度の文を構成することができる。でも、それでいいのか?自分の母国語である日本語と向き合い、自分の経験や感情を言葉にし、それを紡いで文章にして相手に伝える。その行為は自分自身と向き合うことだと思った。
次に読む本
『ツバキ文具店』 小川糸
雨宮鳩子は古い日本家屋のツバキ文具店で、亡くなった祖母から継いだ代筆屋をしている。人から依頼された思いを手紙に代筆するのだ。お悔み状、離婚報告の手紙、絶縁状、ラブレター…。個性豊かな人たちが鳩子のもとに訪れ、鳩子はその思いを丁寧に代筆する。古都鎌倉を舞台に、初夏から始まる小さな文具店の一年間の物語。

手紙は言葉を選ぶことによって人の気持ちを動かすことができる、まさに心理作戦だと思う。鳩子が会ったことのない相手を想像し、紙の質感、筆、便箋や封筒、切手にまでこだわるプロフェッショナルさに感嘆の一言。時には感情的になったり、挫折しながらも書き上げた数々の手紙は、鳩子のあたたかさが伝わってきて、思わず涙してしまいました。
この本のもう一つの魅力は”鎌倉”というロケーション。ツバキ文具店は山側にあって、神社や竹林、カフェが鳩子の定番のお散歩コース。材木座や由比ヶ浜まで足をのばし、老舗のお菓子屋さんや、定食屋、地元民に人気の市場に出かけることも…。観光地ではない”鎌倉”の景色が鮮やかに描写されています。
おススメポイント

『AIが書けない文章を書く』の著者・前田氏は「文章を読んでもらうことは相手の時間を奪うことだ」と言っていた。
だから、文章を書くなら『肉まんよりミルフィーユ』!!
一つの文に様々な要素(具)がつまった肉まん文章よりも、一つの要素を薄く何層にも重ねたミルフィーユ文章の方が、相手にとっても美味しいと感じるそう。なるほど…と思う文構文のヒントがつまった一冊。
ツバキ文具店代筆屋の鳩子が書く手紙はまさにAIには書けない文章!人間にしかない想像の力や繊細さが大いに発揮されています。特に最後の亡き祖母に宛てた手紙は涙腺崩壊です。
前述した、鎌倉の魅力がたっぷりつまった一冊で、「ツバキ文具店の鎌倉案内(幻冬舎文庫)」を片手に、鳩子のお気に入りの市場やカフェ、神社巡りをしてみては…。


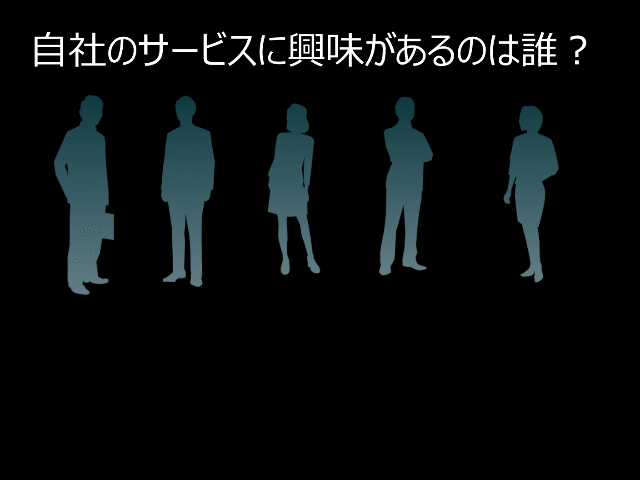 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す