あらすじ
「文章を書く」とは?「ことばの力」とは?
ChatGPTなどの生成AIの台頭で、あらゆる「ものづくり」の価値観が揺らぐこの時代。「文章を書く」という技術と、その意義を原点から見つめ直すきっかけになる一冊。

著者は朝日新聞で40年の校閲歴を持つ、文章のプロフェッショナル。ことばや文章に対する眼差しが優しくも鋭く、私が普段いかに「ことば」をテキトーに使っているかを思い知らされました。
学校で習わなかった文章を書くときの「お作法」、個人がメディアとなってことば=情報を発信する「責任」、そして自分にしか書けないストーリーを届けることの「意義」…この本からは、それらが静かな熱を伴い、伝わってくるのです。
私は普段、薬剤師として患者さんの情報を記録する薬剤服用歴(薬歴)を書きますが、この本で学んだことは仕事でも活かせます。独り善がりにならず、いかに伝わる文章を届けるか…職業が「物書き」でなくても、ことばと向き合う日々の姿勢がとても大切なことに気付かされます。人は皆、「文章を書く」ということから離れては生きていけないのでしょう。
正直、ChatGPTの「文書」はすごいです。その滑らかで豊かな回答に感動するとともに、子どもたちが生きる未来への不安も覚えます。未知のパラダイムの中で生きる我が子に、時間をかけて自分のことばで文章を生み出す必要性をどう伝えるのが良いのか?いや、むしろそれは時代錯誤なのか…?
だけど、作者のことばに触れて、どんなに時代が変わっても、人は「文章」を書く生き物なんだ…という確信を得ました。
ことばを紡いで文章を書けば、どうしても自らをさらすことにもなります。どんなに取り繕っても、その人の思考が滲み出ます。思考は言葉で構成されるからです。自分の使うことば以外に、自分の思考を伝えることができないからです。
そしてどんなに哲学的、形而上的な話であっても、そこには必ず人が存在します。人が存在する限り、そこに状況、行動、変化の理由があるはずです。
個人的な文章もその思いを記録し続ければ、時間の経過によって余分なものが削ぎ落され「芯」が立ち現れます。それを客観的に見て、長期的な判断をすることが「時」を記す意義です。
本文より

私は、著者が高校時代に陥った「精神的過呼吸」のエピソードが印象的でした。こんな風に心の中で足掻くような、もがくような感覚は、誰もが経験した覚えがあるのではないでしょうか?「書くこと(アウトプット)」は自身を俯瞰し、軌道修正するための「処方」となるのです。
悩みのない人なんていません。心に抱えるものを文章として組み立てる中で、自らの考えをまとめる。その考えを課題とし、解決方法を模索する…そんな内面の軌跡を「教養」と表すところに、著者の愛を感じます。正しさや誤りを超えたところで、人はきっと文章を書くことから離れられないのでしょう。
思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。
マザー・テレサ
言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。

本文にあった「WHY」の使い方の重要性…それは生き方にも通じそうです。思いの源泉である「ことばの芽」を引き出す作業は、自らを深掘りし、唯一無二の「わたし」に辿り着くための歩みでもあります。決して楽な作業ではないけれど、そこにはきっとAIに代替できない輝きを持った原石が埋まっています。その原石を持ち寄って、人は人と繋がり、より良い未来を創ることができるはず…そう考えたとき、「ことば」と共に飛び出す明るい我が子の姿が想像できました。
ChatGPTをはじめとする生成AIの技術は素晴らしいです。だからこそ、人は「文章を書く」ということに、もう一度しっかりと向き合う必要があるのでしょう。AIをツールとし、自らがメディアとなり、そのストーリーで世界を動かすために。
次に読む本
伝わる・揺さぶる!文章を書く(山田ズーニー)
進研ゼミで高校生の小論文に関する指導実績を持つ作家・文章表現教育者の山田ズーニーさん。彼女が伝える、良い文章を書くための「戦略」。「目的」と「結果」を重視し、7つの視点から実践的に紹介される文章術は、年齢を問わず、今を生きる人々のあらゆる場面で活躍すること間違いなしです。

10年以上も前、校正をしていた夫から勧められた本。文章術の本かぁ‥と軽く読み始めたら、目からウロコが何枚もポロポロと落ちたことを覚えています。
この本のゴールは、「あなたの書いたもので、読み手の心を動かし、状況を切り拓き、望む結果を出すこと」…「機能的な文章を書く」という視点を、私はここで初めて知りました。もっと早く知っていれば、片思いのあの人に「結果の出るラブレター」を書けたのに…くうぅ。。
良い文章を書くための作業が具体的で、根拠があり、実用書として素晴らしいです。しかし、それだけではありません。この本を読む中で、私は何度も「ちゃんと自分の人生を生きている?」と問いかけられたように感じました。
私はものを書くとき、絶対、「…たらどうしよう」の気持ちで書かないようにしている。(中略)それは「恐れ」を行動動機とすることになるからだ。
自分の腑に落ちるまで、自分の生き方にあった言葉を探し、言葉を発見し、自分を偽らない文章を書くことによってのみ、読み手の心は動くのだ。
本文より

テキトーな生き方からは、うわべを取り繕ったようなテキトーな文章しか生まれません。人を動かすような文章を生み出すには、まず自分を偽らずに、自分の人生をしっかり生きる必要があるのだ…と衝撃を受けました。「正直という戦略をとる」…そのためには、周りの空気に流されない自分の軸を見つける必要があるのです。「文章を書く」以前に、それがいかに難しいことか…。
この本にある問いかけに、自分なりの答えを出していくことで見えてくるものがあります。それはきっと、誰一人同じものはないでしょう。それがきっと、「わたしらしさ」と「わたしが文章を書く意味」。それを確認し、実生活に戻ったとき、「この世界と関わる(生きる)姿勢」が変わるように私は感じました。
おススメポイント

思春期の頃、私は女友達との付き合いが苦痛でした。「ホンネ」と「タテマエ」の区別がつかなくて‥。見たままの世界が信じられなくなっていた当時の私にとって、読書はある種の救いでした。本は著者とのコミュニケーションツールだったのです。「文章」とは、書き手の世界を、読み手の心に立ち上げるもの‥その世界で遊び、鍛えられ、支えられてきた人が、いかに多いことでしょう。
それなのに「読み手」ではなく「書き手」になったとき、私たちは途方に暮れます。良い文章を書こうとすればするほど、実際に綴る文字には生命が宿りません。なんならChatGPTの方がよっぽど早い・多い・上手い!楽をするなら、この技術を使わない手はありません。タイパ重視の今の時代、なんでしんどい思いをしてまで、自分の頭で考えて書かなきゃいけないんだ…。しかし、この2冊の本を読むことで、「文章を書く」ことの本当の意味と価値が分かってくるのです。
「文章を書く」ことは、「自分の人生を生きる」ということ。ことばと真摯に向き合うことは、自分自身を見つめ直す作業です。私たちは問い続ける。答えが見つからなくても、自らに問い続けることで、人はきっと成長できる。思考の揺らぎを持て余し、反論や拒絶に心を痛めつつ、「わたし」を創り上げている想いの源流を探し求める…それはAIには出来ない、人間らしい営みに違いありません。
当たり障りのない八方美人な文章を書く方が、きっと楽なはず。だけど、そこからは何も生まれない。社会と関わるために、自分の「意見(ことば)」を責任を持って発信する…これからの時代に求められるのは、そういう能力と勇気なのでしょう。便利な道具に振り回されて、ハリボテのような人生を送らないために。
思春期における私の孤独を救ってくれたのは、書き手の「ことば」と「生き方」でした。誰かに届けるために必死に書かれた「文章」が、受け手の心で展開されたとき、それはかけがえのない意味を持ちます。書くことで自分の世界を構築し、書くことで誰かの世界と繋がっていく。そこに広がる豊かな世界は、生成AIの力だけでは決してたどり着けません。「文章を書く力」を強く信じるお二人の「ことば」が、混沌とした時代を生きる人々への応援歌のように私は感じるのです。


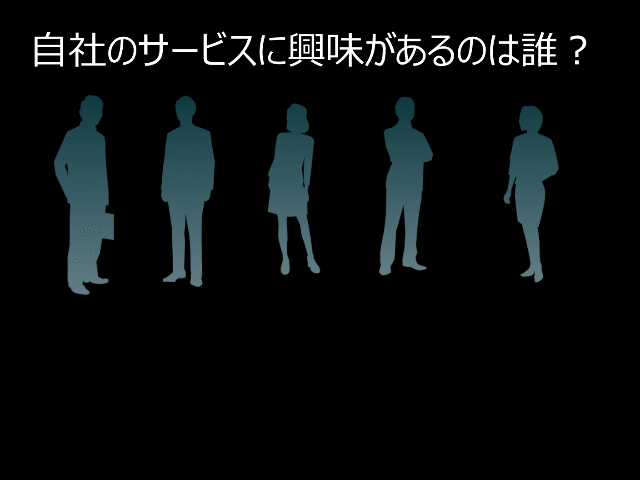 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す