あらすじ
3.11を機に日本は「大変動の時代」に突入した。2030年代にくるであろう「南海トラフ巨大地震」は、東日本大震災をはるかにこえた被害を日本にもたらすことは明白であり、さらにその震動によって誘発された富士山が噴火する可能性も高い。
地震と火山の国で生きる我々にとって、今、すべきことは?
京大名誉教授である鎌田氏が、地球のはじまりから地震と噴火のメカニズム、この国で暮らす私たちに不可欠である地学の知識をていねいに解説する。

「地学」とはほど遠い生活をしている私でも、最後まで楽しめて読めた。文章も語り口調で、図解も多い。時折、生徒からの質問もはさまれていて、大学で講義を受けているようなライブ感もある。いったい鎌田教授ってどんな方なのだろうと検索してみたら、かなりオシャレな素敵な人だった。
「過去は未来を解く鍵」 地学では過去におこった現象を解析することで未来の予測を立てる。46億年前、火球だった地球から海が出現し、なぜ生命が誕生したのか…から本書は始まる。地球の46億年を一年カレンダーにしたものに衝撃をうけ、地学って面白い!そして私はなんてちっぽけなんだと!思った。 鎌田教授は、地学は長いスパンで自然現象を捉える「長尺の目」が大切であり、正しい地学の知識をもつことが、この”地震・火山大国”日本で生きのびていく術なのであると説いている。
次に読む本
「それでも、海へ 陸前高田に生きる」 安田菜津紀
3.11 岩手県陸前高田の港町、根岬。一瞬にして大津波がこの町をのみこみ、たくさんの命が失われた。「もう、海に出るにはやめよう」漁師の菅野さんは変わり果てた港をみて思った。しかし、「じっちゃんがとってきた白いお魚が、もう一回食べたい」と言う孫の言葉に、再び漁に出る決意をする。
自然の猛威と恩恵を受け入れ、少しずつ活気をとりもどしていく海とともに生きる人々の姿をていねいに描いた、ノンフィクションの写真絵本。

著者はフォトジャーナリストの安田菜津紀さん。
写真から、海の美しさ、復興に向けてうごきだす根岬の人々の表情が、ショートフィルムを観ているかのように伝わる。大津波に何もかも奪われても、そこで生きようとする人たちのひたむきな姿に涙がとまらない。 前記した地学の本でも、海の出現により生命が誕生したとあるように、海があるからこそ私たちは生きているのだと思った。
震災から14年。孫のしゅっぺ(修生)君、じっちゃんの背中をみながらどんな人に成長したのだろう。じっちゃんはまだ漁に出ているのだろうか。 児童書ではあるが、是非、大人にもよんでもらいたい。また、震災を知らない子どもと一緒に読むのもいい。

『「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る大人のための地学の教室』
3.11から14年。震災を知らない世代も増えていく中、これから起こるであろう巨大地震に何をすべきか。防災準備も必要だが、知識をもって身を守ることも大切なのだと教えてくれた。
『それでも、海へ 陸前高田に生きる』
3月11日がくるたびにひらく絵本。何回みても、毎年、こみあげてくるものがある。テレビに映った津波の映像は衝撃だったし、その後の非日常の日々を思い出す。


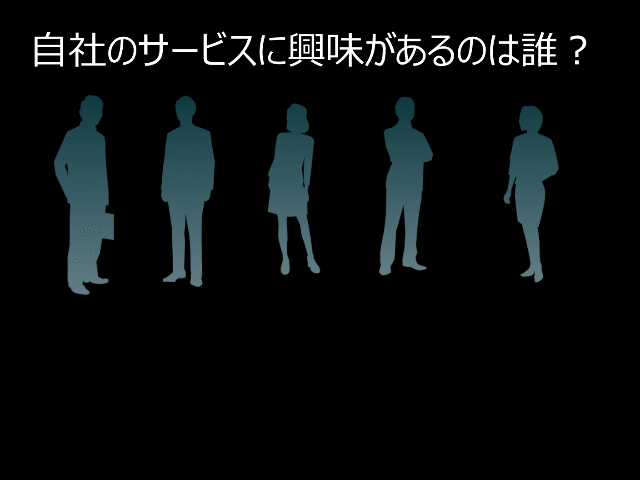 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す