あらすじ
60年に一度訪れる年、「ひのえうま(丙午)」。丙午産まれの女性は災いをおこす…江戸時代に拡散された迷信により、高度経済成長の只中、1966年の出生数が史上最低を記録した。ただでさえ少子化が進む昨今、2026年に丙午がやってくる。各時代の丙午に生まれた女性の人生は、実際どのようなものだったのか。江戸から昭和までの丙午がもたらした日本独自の社会現象を、自ら昭和丙午生まれの社会学者が文献やグラフで解説する。

間引き、中絶、子捨て、生年変更、自殺…丙午の迷信にふりまわれた江戸から昭和の女性たち。始まりは江戸の『八百屋のお七』という女の恋愛のもつれから生じたよくある噂話だった。360年前の噂話が令和の出生数に影響するはずないと思うが…。そもそも丙午って?と知らない世代も多いはず。
しかし、この本には丙午がもたらした社会現象を文献やグラフとともに、明確に著されている。丙午と各時代の出生数や女性たちの生き方が興味深い。実は昭和の丙午生まれの女性は少しだけラッキーだったのかも⁉
今はSNSなど様々なメディアで噂が拡散されているが、拡散されすぎて、360年後も残っている噂なんてほとんどないのだろう。
次に読む本
森へ行きましょう(川上弘美)
1966年丙午に生まれた留津とルツ。
同じ日に生まれ、同じ名前の二人の女性が選択していく人生は全く違うが、いたかもしれないもう一人の『自分』。
深い森で何度もさまよい分かれ道に立った時、もしも別の道を選んでいたら、違う人生があったのかもしれない。パラレルワールド(平行世界)に生きる二人の女性の運命と生涯描く長編小説。

初恋、進学、就職、結婚、出産…人は生きていくなかで様々な分岐点がある。文芸肌の留津、研究者のルツ、性格も家庭環境も異なる二人の“るつ”の人生が交互に書かれ、長編だがよみやすい。ジュリアナ東京、サリン事件、東日本大震災など二人の成長とともにその時代背景も垣間見える。
選んだ道、選ばなかった道、その時に一緒に歩いてくれた人は誰だっだのだろう。
二人の間で同じ友人や恋人もシンクロするので、脳内整理が追い付かずメモが必要だった。
おススメポイント

『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』 丙午を知らない人にもグラフを用いていてわかりやすい。江戸~令和までの社会情勢も学べる。
『森へ行きましょう』 大好きな川上弘美さんの長編小説。今までの川上ワールドとはちょっと違うテイストだが、面白くてすいすい読める。二人の成長に自分を重ね、懐かしい気持ちになる。


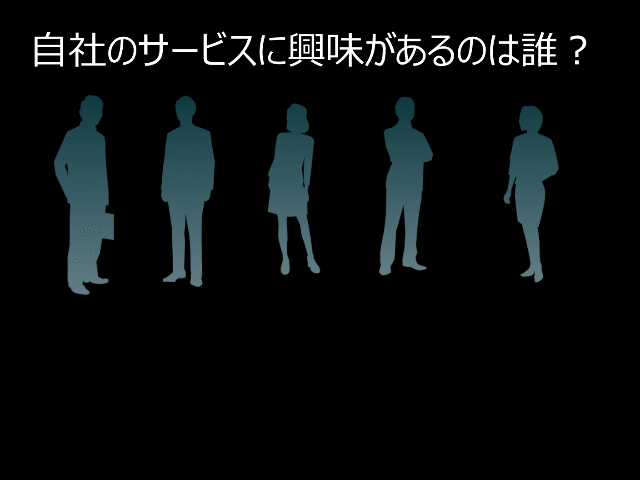 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す