あらすじ
コロナ禍真っ只中の長野県にある病院の医師・看護婦、その家族たちの物語です。すでに東京などの都市部では、パンデミックとなりつつあった頃、長野県でも感染者が激増し、医療崩壊の危機になる寸前でした。

緊急事態宣言の頃、病院や自宅待機の人たちをテレビで見ることはあったけれど、実際は想像以上に大変だったのではないかと感じました。
著者はお医者さんです。コロナ診療にも関わっていらっしゃったそうで、小説とは言え、かなりリアルに近い物語のようです。
また同じような事態にならないとは限りません。読んだ後は、頭のすみっこに内容を保存しておきたい1冊です。
次に読む本
「命の砦」(夏川草介)
「臨床の砦」と同じ病院が舞台の物語です。横浜港に帰ってきたクルーズ船に乗船していた感染者が長野県まで運ばれた頃から、増えつつあるコロナ感染者の受け入れ体制が整うまでを描いています。

「臨床の砦」よりも過去の話で、医師たちが回想する形で物語が進みます。
現在はインフルエンザと同じような扱いをされる新型コロナですが、ほんの数年前までは未知の病でした。未知の病と向きあう医師や看護婦のプレッシャーはどれほど大きかったのでしょう。想像できません。
現在の状態にまで落ち着いたのは、この本に出てくるような医師たちのおかげだと痛感しました。
おススメポイント

新型コロナは、それほど恐れる病気ではなくなりました。しかし、さらに新型が出るかもしれないし、新しい感染症が出るかもしれません。
パンデミックが再度発生したら、病院に行かずに済むように努力していきたいと強く感じました。


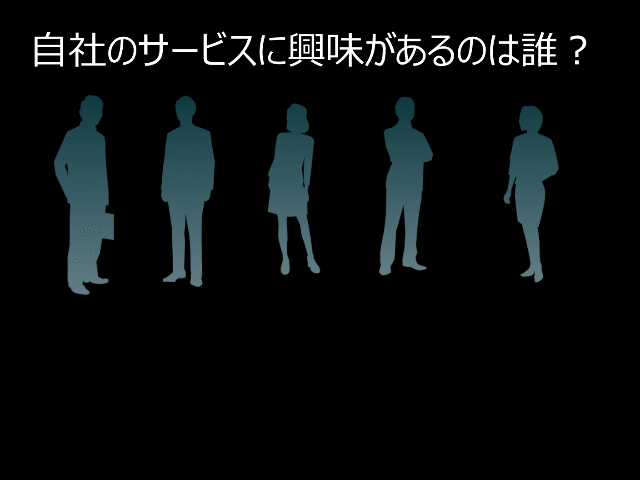 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す