あらすじ
1946年から2019年7月までの間に、死刑執行が確認されたのは714人。加えて、生きている死刑囚が112人。つまり戦後日本において、計800人以上の死刑が確定している。
法律上は死刑確定後6ヶ月以内の執行が定められているが、実際はこの期間は守られていない。執行順もランダムだ。半世紀近く死刑執行を待つ者もいれば、1年で執行される者もいる。各人の執行タイミングは、内閣改造などの政治的要因も絡みながら決められていく。
本書は死刑判決が出た40個の事件ファイルと、死刑囚が残した言葉をまとめた作品。

死刑囚らが残した言葉は、罪を悔いて静かに死を受け入れるもの、冤罪を叫んでも届かなかった悲しい叫び、被害者遺族の感情を逆撫でする発言など、人によって様々です。ただ1つ共通していることは、どれも何かしら感情に訴えかけてくる言葉であること。死刑制度の重みを改めて感じた1冊でした。
次に読む本
死刑について/平野 啓一郎
死刑制度の維持を主張する者は、被害者感情を理由に挙げることが多い。しかし、我々は被害者に本当に寄り添えているだろうか。被害者に適切なサポートがある社会だろうか。
他でもない国家が人権の例外ケースとして、「目には目を」と人を殺すのは適当か。
元々は死刑存置派であった小説家・平野啓一郎が、小説のテーマとして犯罪や死刑制度を扱い取材を重ねる中で、死刑廃止論に至った理由を語る。

死刑存置派の意見にも寄り添いつつも、死刑制度のもつ問題点や論点が、整理されてコンパクトにまとまっています。
”死刑制度の議論の始まりは人権であるべき”、という意見にはハッとしました。確かに議論の始まりがずれたまま、私達は死刑制度を議論しているかもしれません。
おススメポイント

「死刑」というテーマが共通していたことから、この2冊を選定しました。どちらも死刑廃止よりの論調ではあるものの、『死刑囚200人最後の言葉』はセンセーショナルに、『死刑について』は論理的に滔々と、死刑制度の是非を私達に問う作品です。


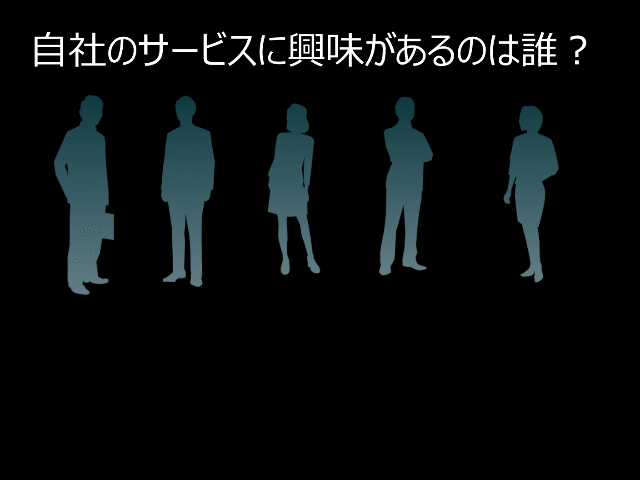 ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
ホームページで興味を持ってくれた見込み客に素早くアプローチ
コメントを残す